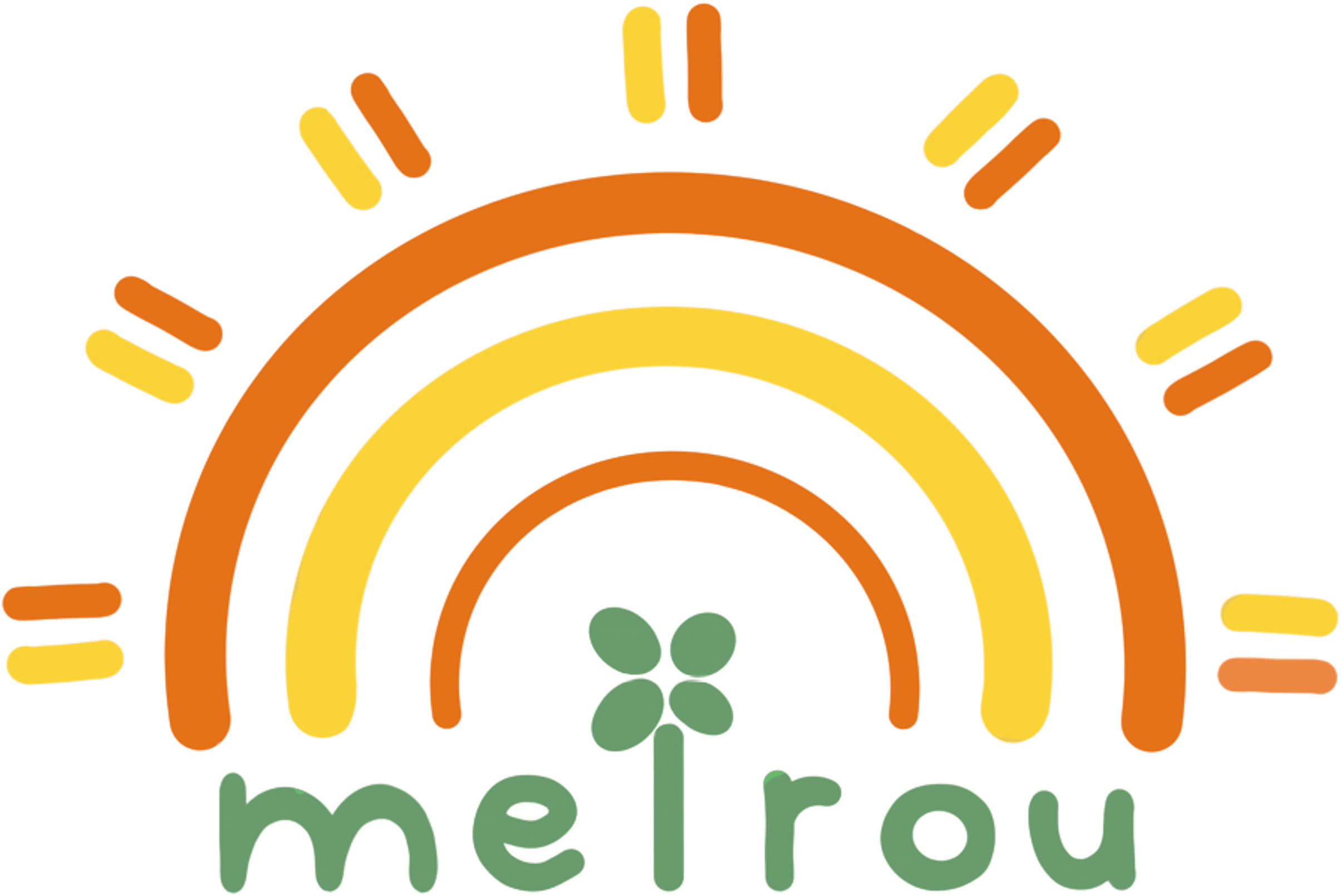第15回【住宅ローンの「借りられる額」と「返せる額」をご存じですか?】
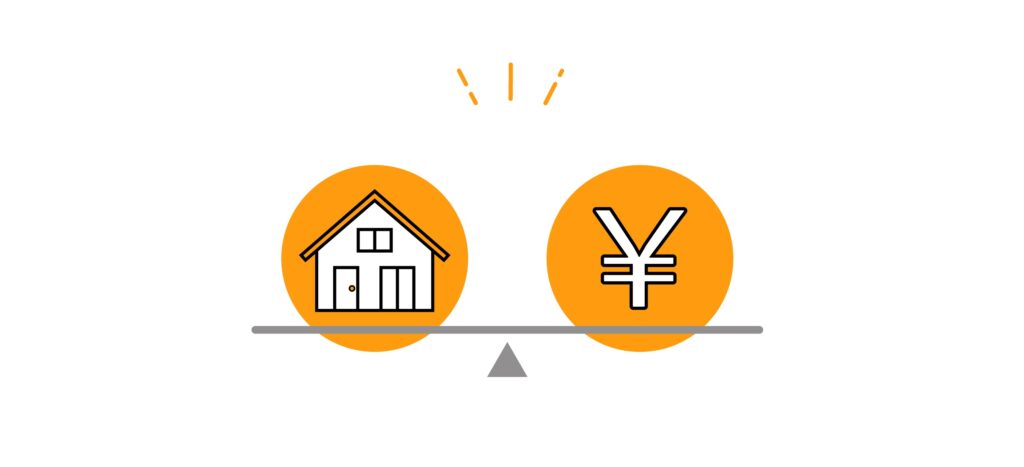
「はじめての不動産売買に 明るく朗らかな未来を」株式会社明朗の千場智樹です。
「夢のマイホーム」を手に入れる際、ほとんどの人が利用するのが住宅ローンです。
しかし、この住宅ローンの借入額をどのように決めるべきかご存じでしょうか?
金融機関から借り入れできる金額には、大きく分けて「借りられる額」と「返せる額」の2種類があります。

この2つの間にはギャップがあるため、この違いをしっかり理解しておかないと、念願のマイホームを手に入れたは良いものの、ローンの返済が苦しくなり、最悪の場合、家を手放すことになってしまうかもしれません。
そうならないためにも、それぞれの金額について詳しく見ていきましょう。
「借りられる額」とは?
「借りられる額」とは、金融機関が「購入者に融資できる最大の金額」を指します。

これは、購入者の年収や、その他の借入状況などに基づいて算出されます。
たとえば、年収450万円、35歳のAさんのケースを考えてみましょう(他に借入はないものとします)。
利用する金融機関の審査金利が2.3%、返済比率が35%以下、返済期間が35年と仮定します。
ここでいう審査金利とは、実際に適用される金利(実効金利)とは異なり、審査のために使われる金利です。
返済比率は、この審査金利で35年間ローンを返済する際に、「毎月の返済額が月収の何%以内であれば融資可能か」を示す割合です。
Aさんの月収は、450万円 ÷ 12ヶ月 = 37.5万円です。
返済比率35%を適用すると、37.5万円 × 35% = 131,250円となります。
つまり、毎月の返済が131,250円以内であれば融資可能と判断されます。
この条件で計算すると、金利2.3%で35年返済(元利均等)の場合、約3,780万円の借り入れで毎月の支払いは131,115円になります。
この3,780万円が、Aさんの「借りられる額」となるわけです。
しかし、この「借りられる額」いっぱいに借り入れをしても本当に大丈夫でしょうか?
返済比率はあくまで金融機関が審査のために独自に設定した基準であり、その枠内だからといって、無理なく返済し続けられるとは限りません。
「返せる額」とは?
ここで重要になるのが、「返せる額」を把握することです。

これは、あなたが毎月無理なく返済できる金額を明確にし、それに基づいて導き出される融資額のことです。
では、「毎月無理なく返せる額」はどのように算出するのでしょうか?
基本となるのは、現在の家賃、駐車場代、電気・ガス・水道代など、毎月支払っている住居費の合計額です。
仮に、現在の住居費の合計が月10万円だとします。
新居では駐車場代がかからず、オール電化と太陽光発電で光熱費が毎月1万円安くなると仮定します。
しかし、年間18万円の固定資産税・都市計画税が発生するため、月換算で1.5万円の支出が増えるとします。
これらの条件で、住宅ローンの返済に回せる月額を計算してみましょう。
現在の住居費10万円 + 光熱費削減分1万円 - 固定資産税等1.5万円 = 9.5万円
新居で現在の生活水準を維持したいと考えるなら、住宅ローンの月々の支払いを9.5万円以内に抑える必要があります。
例えば、金利1.0%で35年間(ボーナス返済なし)の場合、約3,360万円の借り入れで毎月の返済額は94,847円となります。
この場合、無理なく返せる融資額は3,360万円と言えるでしょう。
「借りられる額」と「返せる額」のギャップ
今回のケースで見てきたように、「借りられる額」が3,780万円に対し、「返せる額」は3,360万円と、420万円もの差が生じました。
もし「借りられる額」に近い金額でマイホームを購入し、それでも現在の生活水準を維持したいと考えるのであれば、ボーナス返済を組み込んだり、返済期間を40年に延ばしたりといった方法も考えられます。

何よりも大切なのは、安易に「借りられる額」いっぱいに借り入れをするのではなく、ご自身にとって「毎月無理なく返せる額」をきちんと把握し、身の丈に合った借り方をすることです。
夢に見たマイホームでの生活。
ローンの支払いが始まってから後悔することのないよう、このコラムが皆様の明るい未来を築く一助となれば幸いです。